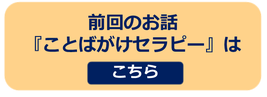最新更新日:2025年7月5日
ダイバーシティ保育(多様性)研修

「一人ひとり」の「個性」が認められる
働きやすい・働きがいのある職場へ

たくさんのご予約・お申込み 本当にありがとうございました。



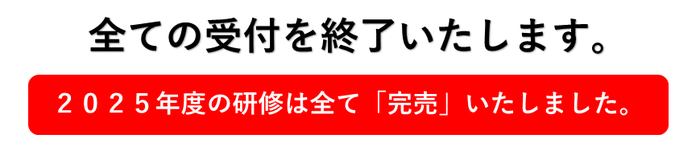

『保育の職場の多様性(ダイバーシティ)』について『ことばがけ』を「テーマ」にアプローチ。今日からできるワークを盛り込んだ『ダイバーシティ保育研修』です。


『新しい研修』について私が「質問」いたします。

研修ナビゲーター:田中ゆり先生
2025年度に初めて、岸本元気先生の研修を受講される先生方もいらっしゃると思います。
そこで私(田中)が代表いたしまして(実は私も今年度初めて受講します!)今回ご用意頂いている「保育の職場の多様性」の研修について内容を細かく質問したいと思います。
教えてくれるのは 岸本 元気 先生です。

岸本 元気- Genki Kishimoto
それでは、よろしくお願いいたします。

「ストレスにならない保育」を変更したのはなぜですか?

田中先生、こんにちは。前回は9月から始まる「ことばがけセラピー研修」へのご質問を頂きありがとうございました。今日は、2025年度から新しく始まる『決めつけない』保育研修についてお話ししたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。遠慮なく聞いてくださいね。

2022年から2024年まで『ストレスにならない保育』という研修を実施してきました。この研修は、もともと「ストレスチェック付きのメンタルヘルス研修」としてスタートしたのですが、2023年から「不適切な保育」の問題が大きく取りざたされ、そこから一度内容を変更して「こどもへの対応に関するストレス」を話の中心として2024年までは実施してきて、70回近くこの研修は行ってきたのですが・・・。
その中でスゴく気になる「ことば」を多く耳にしました。
それが
「ふつう」
です。
「ふつう」はこうでしょ、という「ことば」だけでなく「ADHD」傾向は「ふつう」こういう傾向。「ASD」傾向は「ふつう」こういう傾向。みたいな「ふつう」というのが至る所にあふれていました。そんな中、ある先生が少し「イラッ」とされた表情で、こう言ってたんですね。

うーん・・たしかに

さらに
「ふつう」という「ことば」だけでなく、こどもたちに対してだったり、同僚に対してだったり、はたまた同僚の先生と「保護者」の話をするときにも目立つ「ことば」がありました。
それが
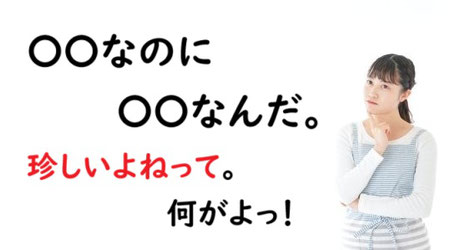
「〇〇なのに〇〇なんだ」。これは「無意識」からでてくる「思い込み」の「ことば」です。
例を出せば、本当にドンドン出てきます。「男の子なのに〇〇なんだ」「女子なのに〇〇なんだね」「若いのに〇〇だよね」「年を取っているのに〇〇だよね」「独身なのに〇〇なんだ」「結婚しているのに〇〇なんだ」・・・もう無限にこの「フレーズ」は出てきます。
これは「世の中」の流れとは
全く「逆方向」に向かっている「ことば」
です。
「メンタル不調」も
「人間関係」による「離職」も
「職場のハラスメント」も
その根底には、必ず
この『ことば』があります。
これが「研修」を切り替えた大きな理由です。

うーん・・そうだったんですね・・

「ふつう」という言葉。やっぱり『弊害」が生まれますか?
生まれます。

「相手」に
「ふつう」を求めると
そこからは
「〇〇すべきだ」
が生まれます。
保護者ならこうあるべきだ

この月齢ならこうあるべきだ
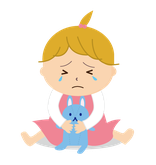
保育士ならこうあるべきだ

そんな「思い」が
生まれてしまうのです。

これが今回の「研修テーマ」です。

是非それ聞いてみたいです!

最後に「研修」の具体的な内容を教えてください

今回の「研修テーマ」は

です。

さらに「前半」「後半」の「2つのタイトル」で構成されています。
●前半テーマ

人には『目にみえる部分』と『目にみえない部分』があります。例えば『目にみえる部分』は、「性別」「国籍」「年齢」「見た目」「雰囲気」「障がいの有無」のようなもの。『目にみえない部分』は「性格」「価値観」「信仰」「経歴」「スキル」「働き方」「趣味嗜好」「家族構成」などがあります。
『目に見える部分』だけを見て、「あの人はこういう性格だ」「あの人の能力はこのくらいだ」「あの人は見た感じ、仕事ができそうにない」「おそらくあの人は独身だろう」など『目に見えない部分』がわかるはずがありません。
「決めつける」ではなく
一人ひとりのニーズを
理解する
「ワーク」をご用意!

●後半テーマ
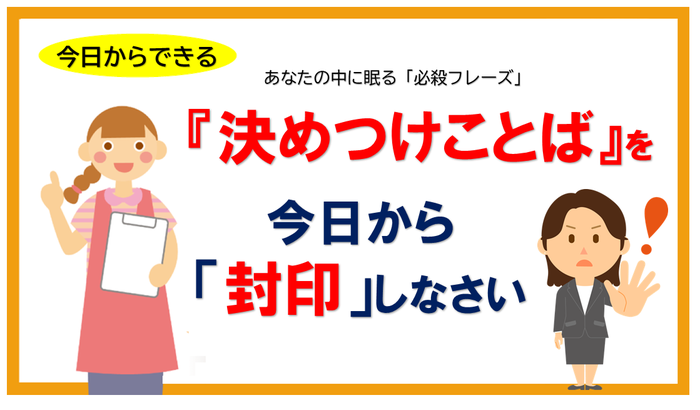

みなさんは『必殺フレーズ』持ってますか?
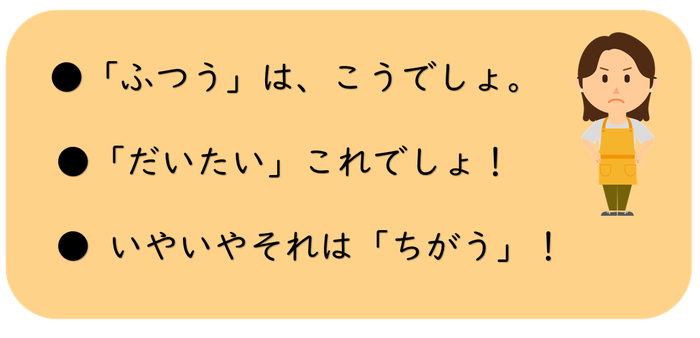
だったり
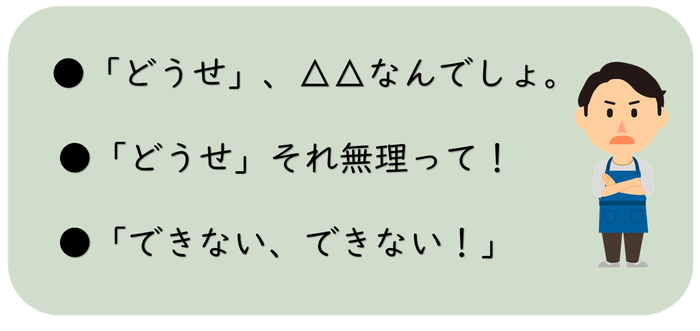
最後のダメ押しは

こうした
「決めつけことば」を
変えるための「ワーク」をご用意!

「こんな内容」で構成しています。

うわー!!
研修がとても楽しみになりました。
ありがとうございました!

はじめまして。
親と子のメンタルヘルス 研究所
岸本元気です。

保育士、幼稚園教諭の先生方へ。はじめまして。岸本元気です。
僕は福岡にあります「親と子のメンタルヘルス研究所」で「感情開放療法(ことばを使った感情開放)」というセラピーを「メンタル不調を抱えた保護者の方」や「行動面で気になる点が多いこどもたち」「不安感の強い保育者の方」向けに行っている「ことばがけのセラピスト」です。
今回お話する内容は「保育の職場の多様性」です。
社会の人材不足が進んでいる中、『ダイバーシティ(多様性)』の推進はどんどん加速度がついています。もちろん「保育の場」も例外ではありません。「一人ひとりの個性が認められる。それぞれの先生が持つ能力が最大限発揮される。働きやすく、働きがいのある保育の場」は、保育所に勤務される職員の先生だけでなく、保護者からも求められています。
今回は「ことばがけ」を「テーマ」に「今日からできる取り組み」について様々なエピソードを交えてお話しいたします。
みなさんの「保育の場」に少しでも「光」を当てられる研修になるよう準備したいと思います。
たくさんの先生方とお会いできることを、こころから楽しみにしています!!(げんき)
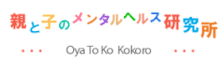
ことばがけコンサルタント
(保育士・精神保健福祉士)
岸本 元気- Genki Kishimoto
一人ひとりが「働きやすく働きがいある」職場を作る

研修内容
人は誰でも「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」を持っています。「一般的にはこうだ」「これまで私はこうやってきた」そうした基準を「他者」に当てはめそうになった時に「立ち止まって自分に問いかけてみる」(本当にそうなの?)そうした「意識」が芽生えると「みんなが働きやすい職場」をつくることにつながっていきます。

(テーマ)「アンコンシャス・バイアス」に気づき『ことば』を変える。
- 自分では気づいていない「ものの見方」や「捉え方」とは。
- 「この人はこういう人だ」って「本当にそう?」
- 「決めつけことば」と「押し付けことば」口にしてない?
- 「ことば」を変えると「意味」が変わる!
(時間)2時間(前半50分・後半50分)

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に気づく「ワーク」
自分では気がついていない「無意識」の「見方」や「捉え方」「歪み」を理解し、自分自身の「モノの見方」や「考え方」のクセに気づき、変えていくことを目指す。
「気持ち」を正直に伝えられる「環境作り」
一人ひとりが抱える「生きづらさ」を理解できる環境。自分の気持ちを正直に伝えられる環境作りを目指す。
お申込みフォーム


※電話でのお問い合わせはご遠慮ください
全ての研修が完売いたしました。そのため「お申込みフォーム」は外しております。
たくさんのご予約本当にありがとうございました。